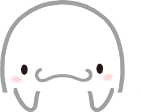くらしお古今東西
静岡県
静岡県と塩
静岡県の蒲原町(現静岡市)や浜名湖周辺では、江戸時代から明治末までは、入浜式や揚浜式による塩づくりが行われていました。
また江戸時代には、内陸の甲州向けの塩は、瀬戸内からまず清水港で陸揚げされ、それから富士川の水運をつかって運ばれました。
なお、戦前から昭和30年代まで、伊豆地区の複数の箇所で温泉熱を利用した塩づくりが行われていました。
塩のsenjutsu
第2回 塩の生産と確保のsenjutsu(戦術)
戦国時代の塩のsenjutsu(戦術)を考える前提として見ておきたいのが、塩の生産地です。海辺であればどこでも塩づくりをやっていそうですが、史料上確認できる事例は思ったより少ないです。
今川・武田・徳川の争奪戦の舞台となった遠江国では、明応7年(1498)の地震と高波で海辺の塩竃が打ち砕かれたといいます(『静』3-244)。塩づくりが遠州灘沿岸で行われていたとみられますが、湖と海を隔てていた砂州が地震と津波によって崩れ、浜名湖が外洋と直接つながってからは、湖岸の宇布見や山崎(旧雄踏町、現浜松市)でさかんになったことが、天正12年(1584)の年貢勘定帳(『静』4-1722)や同15年の請取書(『同』4-1959)の「塩浜年貢」の記載からわかります。
今川氏が長らく本拠とした駿河国では、久能寺が寺領浦で潮を汲んで塩を焼く権利を氏親・氏輝・義元の3代にわたって保証されています(『静』3-921など)。今川氏に代わって駿河を手中にした武田氏は、天正8年(1580)に早船の造立で奉公した功労として、三保(御穂)大明神(旧清水市、現静岡市)神主に塩竃役を免除していますが、そこには塩竃をもつ32人の名が記されています(『同』4-1306)。寺社が塩づくりに関与していた様子は、六浦(現横浜市)に塩浜を持っていた鎌倉の明月院(『神』3-6452)や、塩潟公事を免除されていた堀之内(現横浜市)の宝生寺(『同』3-6766)の事例でもうかがえます。
北条領内では、駿河国から伊豆国にかけての江浦湾や内浦湾沿岸の獅子浜、多比(たび)、西浦、長浜、重洲(重須)、木負(きしょう)(いずれも現沼津市)、伊豆半島東南部の白浜(現下田市)などの村々で塩がつくられていました。重洲村では塩竃をさかんにするため、燃料となる薪を村外に売ることが禁じられています(『静』4-1614)。小田原に近い相模湾沿岸の前川村では、塩浜をめぐる百姓同士の争いもありました(『戦北』4-2637)。
永禄9年(1566)、北条氏康は木負村百姓の抵抗を受けて、年貢の納め方を改めます。その中で、畠年貢は雑穀で納めるべきところ、塩竃稼ぎをしたいとの百姓の要求を受け入れて塩での納入に改めたほか、過去2年分未納した年貢米の返済も塩で代納することを認めます(『静』3-3351)。永禄11年の年貢納法では、百姓の要求を受けて畠年貢を3年間塩年貢にすると定めます(『静』3-3457)。村側は塩づくりに力を入れたいと望んでおり、北条氏は民を慈しむという理由でその要求を受け入れています。ただ、3年を過ぎてもなお塩年貢の制度が続いたのかは定かでありません。天正11年(1583)には、北条氏忠が白浜郷名主・百姓中に対し、年貢の一部を塩で納めることになっていたものを、塩の御用はないので米で納めるよう命じ、船で小田原に運ぶよう指示しています(『静』4-1711)。
これらの史料から、北条氏の支配する沿岸部の村などでは年貢の一部を塩で納める制度があったようですが、それは村側の要求に応じた側面が強く、北条氏自身は塩を現物で受け取ることに積極的ではなかった様子がうかがえます。籠城時には決まって兵粮・鉄砲・玉薬・矢といった食料・武器の確保が問題とされますが(『静』3-3532)、生活必需品であるはずの塩はあがってきません。戦国大名のsenjutsu(戦術)において、兵粮米などに比べると、塩の確保の優先度は決して高くなかったのかもしれません。
天正18年(1590)に豊臣秀吉の小田原攻めを籠城戦で迎え撃った北条氏は、物資の確保に難儀します。当初、物資の備えは十分で、3年でも5年でも持ちこたえるといわれていました(「北條記」『続群書類従』21上-528頁)。小田原城下の松原明神の門前の市は活況を呈したと伝え(「北條五代記」『史籍集覧』5-210頁)、塩をはじめとする物資も簡単に手に入ったことでしょう。しかし籠城中の3月には陣中での兵粮の販売もなくなり、雑炊が高額で売られるだけで、野老(ところ、ヤマノイモ科のつる)を掘って食いつなぐ状態でした(『静』4-2379)。一方、豊臣秀吉は20万石の米を清水・江尻(旧清水市、現静岡市)に運び、蔵を立て、惣軍勢に渡すよう命じる(『神』3-9484)など、圧倒的な物資調達力を有していました。秀吉の陣営には日本国中の商人が集まり、諸国の名産や中国・朝鮮からの珍品まで、売られぬ物はないという繁栄ぶりだったといいます(『神』3-9810)。
ここで塩に目を向けてみると、岩付城(旧岩槻市、現さいたま市)に籠城していた松浦康成は、小田原城に籠る城主北条氏房に戦況を伝えるため、北条水軍の将であった山本正次に書状を送りますが、その中で塩樽2つを送られたことに感謝しています(『戦北』5-3734)。その少し前、房総半島の戦国大名里見氏は製塩地の中島郷(現木更津市)に対し、催促の使者を立ててまで1,000俵の塩年貢を納めるよう求めています(『千』3-782頁)。中島郷は北条氏と里見氏に両属する「半手」の村でしたが(『戦北』4-4007)、時期的にみて里見氏は小田原合戦を意識し、自分の手元に急ぎ塩を確保しようとしたものと思われます。籠城戦を前に、どこも塩の確保に苦労し、慌てだした様子がうかがえます。一方の秀吉は小田原落城後、小田原から会津までの横三間(約5.4m)の道の整備と秀吉の御座所の設営などにあたる5名の奉行を任じ、彼らには途中の城々で兵粮と塩・味噌を受け取るよう伝えています(『豊』4-3289)。秀吉の物資調達力は塩のsenjutsu(戦術)という点でも、北条氏をはるかに凌駕していたといえます。
こうしてみると、年貢による調達、籠城による備えのいずれにおいても、戦国大名のsenjutsu(戦術)における塩の優先度は、兵粮(米)や武器に比べると決して高くなかったことがうかがえます。とはいえ、生活必需品であることにかわりない塩を、戦国大名はどのように調達していたのでしょうか。そこで注目されるのが、第1回の浅井氏の事例で見たような商人を通じた入手方法です。次回は、商人と塩の動きから見ていくことにしましょう。
阿部浩一(福島大学行政政策学類教授)
注)略記した出典は以下の通りです。数字は巻-史料番号ないし掲載ページです。参考になさってください。
『静』=『静岡県史』資料編中世3・4、『神』=『神奈川県史』資料編3古代中世3下、『戦北』=『戦国遺文後北条氏編』1~6、『千』=『千葉県の歴史』資料編中世3、『豊』=『豊臣秀吉文書集』1~8
これまでの連載はこちら
第1回 戦国大名のsenjutsu(戦術)と塩の関わり(滋賀県のページ)
続きはこちら
第3回 塩の流通・商人とsenjutsu(戦術)(山梨県のページ)
第4回 senjutsu(戦術)としての塩留(埼玉県のページ)
第5回 塩の効能とsenjutsu(戦術)(神奈川県のページ)
最終回 戦国を生き抜いた武将たちと塩づくりのsenjutsu(戦術)(千葉県のページ)
(塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会事務局より)
今回の記事については、対象が現在の静岡県のほか、神奈川県、埼玉県、千葉県等にまたがりますが、主な記述対象である静岡県のページに掲載しています。
塩を手に入れるための工夫
流下式による塩づくりの計画
江戸時代には、甲斐(山梨県)向けの塩は富士川の水運を使って運ばれていましたが、江戸時代末に、甲斐向けの塩をつくるため、富士川の河口部で流下式による塩づくりが計画されたことがありました。
参考文献:『日本塩業大系 近世(稿)』
塩づくりの工夫
ヨードの副産物としての塩づくり
ヨード(沃素)は、私たちが生きていく上で欠かせない微量元素のひとつです。戦前、現在の賀茂郡南伊豆町では、海藻からヨードの生産が行われていましたが、その副産物として塩づくりも行われていました。
なお、海外では、ヨード不足を解消するため、食用塩にヨードが添加されることがありますが、私たち日本人は、ヨードを含む海藻類をよく食べるので、塩にヨードを添加する必要はなく、ヨードは食品添加物としても認められていません。
参考文献:「追想 沃度副産塩」井上良之助(『そるえんす』№21)(※外部リンクが開きます)、『塩の事典』橋本壽夫