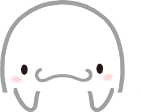くらしお古今東西
大分県
大分県と塩
中世には、豊前の宇佐八幡宮や、豊後の由原八幡宮の神事用の塩をつくるための塩浜があったことが記録に残っています。
江戸時代以降、周防灘沿岸や現在の国東市、杵築市、佐伯市等に入浜式塩田が築造され、さかんに塩づくりが行われるようになり、塩田による塩づくりは昭和30年代まで続きました。また戦時中から昭和30年代にかけては、温泉熱を利用した塩づくりも行われました。
参考文献:『大分県塩業史』仲 定之
塩づくりの歴史
大分県における古墳時代~平安時代の製塩
大分県における最初の塩づくりは、塩分濃度を高めた海水を小形土器(製塩土器)で煮沸・煎熬(せんごう)する「土器製塩」による。大分県は全体としては山地部が多いが、北部は周防灘に、中部は別府湾・伊予灘に面している。南部は豊後水道に面しており、日豊海岸のリアス式海岸が発達している。
土器製塩は弥生時代終末・古墳時初頭に始まる。製塩土器はコップ形に脚台部が付いたもので、体部はタタキ調整されている。おそらく、備讃瀬戸地域(岡山県・香川県)の土器製塩技術を導入したものであろう。県内各地の集落遺跡から製塩土器が多数見つかっており、塩が入った製塩土器が内陸部に搬入されている。塩生産遺跡はまだ明確には確認されていないが、製塩土器の特徴などから大分県産と推定され、県北部・中部の海岸部に存在していた可能性が高い。県内の製塩土器の分布状況から見ると、塩生産遺跡の数は少なく、小規模な生産と考えられる。古墳時代中期になると、内陸部の大分市若宮八幡宮遺跡・毛井遺跡などの集落遺跡から製塩土器が出土している。製塩土器の形態は小形のコップ形土器に変化している。これらの製塩土器は、どこの塩生産地から搬入されたかは速断できないが、一つは大阪湾沿岸部から、もう一つは県北部・中部にある海岸部の塩生産地からの、二つの考えがある。製塩土器の諸特徴からは、両者が混在していた可能性が高い。そうであるならば、大分県では古墳時代中期にも、小規模な塩生産が行われていたことになる。古墳時代後期になると、土器製塩による塩生産の状況は不明になる。後期には塩生産はしていなかったのであろう。内陸部の集落遺跡からは、山口県産の製塩土器が少数であるが出土しており、塩は山口県から供給されていたと推定される。
飛鳥時代から平安時代前半には、製塩土器の形態が深鉢形・円錐形あるいは砲弾形(布目圧痕)に変化する。深鉢形・円錐形土器や砲弾形(布目圧痕)土器は、堅塩(きたし)作成専用土器で、甕形(玄界灘式)土器で煮沸・煎熬して作成した塩や塩田技法で作った粗塩を、深鉢形・円錐形土器や砲弾形(布目圧痕)土器に詰めかえて焼き、堅塩を生産している。塩生産遺跡は未確認であるが、北部・中部の海岸部に存在していたと推定できる。原材料となる塩の作成技法は、甕形土器によるかあるいは塩田技法によるかは不明である。平安時代後半になると、土器製塩による塩生産遺跡や堅塩土器出土遺跡は未確認であり、おそらく土器製塩は消滅したのであろう。以後は、塩田による塩生産が本格的に展開することになる。
大分県では、弥生時代終末・古墳時代初頭に土器製塩による塩生産が始まった。以後、古墳時代中期まで行われたが、生産量はそれほど多くはなかった。古墳時代後期になると土器製塩は断絶したが、近隣の山口県から塩を搬入していた。その後、再び飛鳥時代~平安時代前半まで、塩生産が行われたが、そのほとんどは県内に供給するものであった。
岩本正二(日本塩業研究会会員)
塩にまつわる人物
古庄安右衛門重信
号は拙翁。姫島の庄屋。島民の困窮を救おうと、寛延3(1750)年、1町5反歩の海面を埋め立てて塩田を築き、塩づくりをはじめました。塩づくりのほか、周防(山口県)から甘藷(サツマイモ)を導入し、ここでも島民の生計に寄与しました。
参考文献:『大分県塩業史』、『塩と碑文』水上 清
塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会会員
全国塩元売協会会員
- 大分塩業有限会社