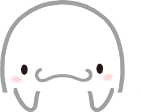くらしお古今東西
埼玉県
埼玉県と塩
内陸の埼玉県には、塩づくりの記録はほとんどありません。
江戸時代には、行徳塩(千葉)や江戸に運ばれた瀬戸内の塩(いわゆる「下り塩」)が、江戸から運ばれました。例えば川越方面には、荒川、新河岸川の水運を利用して川船で運ばれていました。
塩のsenjutsu
第4回 senjutsu(戦術)としての塩留
第4回は「塩のsenjutsu(戦術)」のタイトルにもっともふさわしく、一番わかりやすい、戦国大名の塩留について見ていきます。『日本塩業大系 原始・古代・中世(稿)』などの先行研究で既に利用されている史料ばかりですが、あらためて紹介していきましょう。
塩留というとよく知られているのが、今川氏・北条氏による塩留に苦しむ武田信玄に手を差し伸べた、上杉謙信の「敵に塩を送る」話です。これは江戸時代に越後国の塩商人が信濃国での商圏を守るためにつくられた話ではないかという説があり、具体的には長野県のページの記事(「敵に塩を送る?」落合 功)をご覧ください。
武田氏に対する塩留が実際にあった例と考えられているのが、永禄10年(1567)8月17日に葛山氏元が芹沢玄蕃允・武藤新左衛門尉・鈴木若狭守の3名に対して塩荷の流通を留め、それまでに差し押さえた塩を納めるよう命じたものです(『静』3-3410)。
葛山氏は北条・武田・今川の戦国大名と領域を接し、婚姻関係で結ばれた北条氏の支配方式を導入しつつ今川氏の公的支配を受け入れる、両属の存在でした(有光友學『戦国大名今川氏と葛山氏』)。芹沢氏は茱萸沢(ぐみざわ、静岡県御殿場市)で問屋として、武藤氏は神山(こうやま、同市)で名主・問屋として、鈴木氏は竹之下(同県小山町)で、それぞれ伝馬差配などに関わっていましたが、いずれの場所も甲斐国につながる重要な交通路上にありました。芹沢氏は永禄6年3月以降、須走口(すばしりぐち、同)の関で富士山に参詣する人々や荷物の通行を管理するよう、葛山氏から命じられています(『静』3-3120など)。須走は甲斐国へのルート上にもあり、籠坂峠を越えて山中湖から吉田(山梨県富士吉田市)に至り、黒駒筋につながります(黒駒筋が塩の流通路であったことは、本連載の第3回(山梨県のページ)をご覧ください)。塩留の命じられる直前の永禄10年6月には、芹沢氏は甲斐国郡内地方(山梨県東部、大月市・都留市など)の小山田信茂から年間あたり100疋の馬の通行を免許されています(『同』3-3400)。芹沢氏は甲州方面との流通で大いに利益を上げていたのでしょう。そして8月3日には葛山氏元より、古沢市(御殿場市)で商売をした商人が茱萸沢を通らなかった場合は見つけ次第に馬・荷物を押収することを認められています(『同』3-3405)。こうしたことから、永禄10年の葛山氏の塩留は武田氏に対するものと考えられています。
こののち、永禄11年12月に武田信玄が駿河に侵攻し、今川氏真は遠江国懸川城(静岡県掛川市)に敗走します(『同』3-3509など)。北条氏は今川氏を救援するために出兵し、北条氏と武田氏が戦火を交える中、永禄12年6月、北条家臣の大藤政信は敵国に塩荷を運搬する者たちを討ち捕り、氏真に功を賞されています(『同』4-36)。これも武田氏に対するもので、武力による塩留の一種と考えてよいでしょう。
武田氏に対する塩留の例としてもう一つよく知られているのが、天正8年(1580)12月に武蔵国鉢形城(埼玉県寄居町)城主北条氏邦が長谷部備前守に対し、塩荷を押さえる範囲を定めたというものです(『埼』2-1052)。その範囲は栗崎(くりざき)・五十子(いかつこ)・仁手(にって)・今井・宮古嶋(都島、以上、本庄市)・金窪(上里町)、神流(かんな)川を境と定められています。約1年前の天正6年12月末には宮古嶋衆と倉賀野衆が合戦に及び、吉田政重が功を挙げたことが氏邦から氏政に伝えられており(『同』2-973)、北条氏と武田氏が境を接する地域でもありました。長谷部氏が塩留を命じられた要所を結ぶラインの南側一帯に位置する、深谷上杉氏の深谷御領分の榛沢(はんざわ)・沓掛(くつかけ、以上、岡部町)・阿那志(あなし)・十条(以上、美里町)での塩留は無用であるとされ、さらに半年間は北条方の忍城(行田市)城主成田氏の本領である忍御領にて乱暴を働くことを厳しく禁じられています。以上から、塩留は北条氏と対立する武田氏に向けてのものと考えられています。
長谷部氏の詳細は不明ですが、永禄8年(1565)5月に成田氏長が甘糟商人長谷部源三郎の通行権を保障し、当地の足軽であると証明しています(『埼』2-439)。甘糟(甘粕)は鉢形城下にあたるとされています(日本歴史地名大系11『埼玉県の地名』)。また『埼玉県史』の当該史料には「『長谷部文書』に写がある」との注記があることから、長谷部備前守と源三郎は同じ一族の可能性もあります。だとすると、先の塩留の規定を鑑みれば、長谷部氏の商圏は氏邦の鉢形領から上杉氏の深谷御領、成田氏の忍御領までかなり広範囲に及んでいたと考えられます。そして武田領内に塩が搬出されるのを阻止するため、特に境目にあたる地域の要所で塩留の徹底が命じられたのが、先の史料だということになります。この頃は既に武田氏も海のある駿河・遠江両国を領有しており、かつてほど塩の入手に困難をきたしたわけではないでしょう。とはいえ、塩留のダメージは少なからずあったはずです。天正9年8月に武田勝頼が高崎城主和田信業に六斎市の興行を命じた際に、「塩之役」を諸役免除の例外規定の一つに挙げていたことにも(第3回を参照)、塩流通統制への関心の強さが伺えます。
今回ご紹介した事例は、武田領への塩の流入を留めようとする今川・北条といった周辺大名の動きですが、そこで鍵を握るのは、芹沢氏や長谷部氏のような商業流通に関与する人々の存在です。筆者はこのように商業流通に関わって富を蓄積する人々を「有徳人層」と呼び、その実態を追究したことがあります(「戦国期の有徳人層と地域社会」「伝馬と水運-戦国時代の流通の発達」)。第3回で紹介した、相模国当麻で関所の塩荷の通過を管理していた関山氏も同様の存在です。彼ら流通を支える「有徳人層」の実力と協力があってこそ、戦国大名の塩留は実現できたと見てよいでしょう。
阿部浩一(福島大学行政政策学類教授)
【参考文献】
阿部浩一「戦国期の有徳人層と地域社会」(『歴史学研究』768号、2002年)、同「伝馬と水運-戦国時代の流通の発達」(有光友學編『日本の時代史 戦国の地域国家』吉川弘文館、2003年)、有光友學『戦国大名今川氏と葛山氏』(吉川弘文館、2013年)
注)略記した出典は以下の通りです。数字は巻-史料番号ないし掲載ページです。参考になさってください。
『埼』=『埼玉県史』資料編中世2、『静』=『静岡県史』資料編中世3・4
これまでの連載はこちら
第1回 戦国大名のsenjutsu(戦術)と塩の関わり(滋賀県のページ)
第2回 塩の生産と確保のsenjutsu(戦術)(静岡県のページ)
第3回 塩の流通・商人とsenjutsu(戦術)(山梨県のページ)
続きはこちら
第5回 塩の効能とsenjutsu(戦術)(神奈川県のページ)
最終回 戦国を生き抜いた武将たちと塩づくりのsenjutsu(戦術)(千葉県のページ)
塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会事務局より
今回の記事については、対象が静岡県、山梨県、埼玉県等にまたがりますが、静岡県及び山梨県のページには既に本連載を掲載しているので、埼玉県のページに掲載しています。
塩にまつわる習俗
塩地蔵
現在のさいたま市大宮区に、「塩地蔵」があります。昔、娘を連れた旅の途中、大宮宿で病に倒れた浪人がいました。医者の手当ても薬も利かず寝込んでしまった父親の看病を続ける娘の夢枕に、ある日地蔵様が現れ、塩断ちをするように告げました。娘が塩断ちをして地蔵堂に祈ったところ、父親の病は全快し、喜んだ親子はお礼にたくさんの塩を奉納し、その後、人々も塩を供えるようになったということです。
参考文献:『大宮の郷土史』佐藤利夫
馬の知恵
小川町での話である。塩俵を馬につけて川を渡ろうとしたとき、馬は水中深くに入って塩俵の中の塩を溶かしてしまった。これは、馬子が馬を虐待したためだといわれている。こうした話は各地で残されており、宮城県仙台市でも同様な話が残されている。
落合 功(青山学院大学経済学部教授)
参考文献:『塩俗問答集 常民文化叢書<3>』渋沢敬三編
塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会会員
全国塩元売協会会員