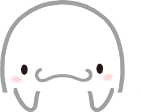各分野の専門家の方々がさまざまな視点から塩と食についてお伝えします。
-
New 暮らしと塩のほんとうの話~公衆衛生の視点から~
第2回 食卓から健康を守る~学校給食と塩のはたらき~ 2025.12.9公開
公衆衛生の視点から見た暮らしと塩の「ほんとうの」話を、德野裕子先生(十文字学園女子大学准教授)にご紹介いただきます。 -
暮らしと塩のほんとうの話~公衆衛生の視点から~
第1回 塩と私の原点~“当たり前”にあった塩の記憶~
公衆衛生の視点から見た暮らしと塩の「ほんとうの」話を、德野裕子先生(十文字学園女子大学准教授)にご紹介いただきます。 -
古代日本の食と塩
イラストレーターの小夜小町さんによる4コマ漫画の連載です。 -
塩が足りないと? 全6回
暮らしに欠かせない「塩」が足りないとどうなるのか、何が起きるのかについて、高田公理(まさとし)先生(武庫川女子大学名誉教授)に、内外の各種文献からご紹介いただきます。全6回の連載です。 -
生命と塩 全6回
辺境生物学者として知られる広島大学大学院教授の長沼 毅先生が、太古の時代から宇宙空間まで、「生命と塩」の関わりを辿ります。全6回の連載です。 -
古代マヤ文明と塩
岡山大学文明動態学研究所の鈴木真太郎先生に、「古代マヤ文明と塩」について、ご紹介いただきます。 -
好塩生物「ハロファイル」
長沼 毅先生(広島大学大学院統合生命科学研究科教授)に、好塩生物「ハロファイル」についてご紹介いただきます。 -
ハルシュタットとザルツブルク
長沼 毅先生(広島大学大学院統合生命科学研究科教授)に、7千年も前から塩を産出していたハルシュタットと、モーツァルトの生地・ザルツブルクについてご紹介いただきます。 -
塩の状態変化を楽しむ料理
青山学院大学文学部准教授の三浦哲哉先生に、「塩の状態変化を楽しむ料理」についてご紹介いただきます。 -
味を引き出すのも、味が活きるのも塩!
早稲田大学教育学部複合文化学科教授の福田育弘先生に、フランス料理と日本料理における塩について、ご紹介いただきます。 -
塩とイタリアの食文化
ノンフィクション作家の島村菜津先生に、塩とイタリアの食文化についてご紹介いただきます。 -
塩づくしの生活
砂野 唯先生(広島女学院大学専任講師)に、エチオピアのフィールドワークで体験した「塩づくしの生活」についてご紹介いただきます。 -
農家の休憩と漬物
京都大学人文科学研究所准教授の藤原辰史先生に、「農家の休憩と漬物」について語っていただきます。 -
血と塩
大阪大学大学院教授・檜垣立哉先生に、「血と塩」について語っていただきます。 -
塩にぎり
遠藤哲夫さん(フリーライター)に、「塩にぎり」のおいしさについて語っていただきます。 -
日本料理の塩加減
龍谷大学大学院教授・和食文化国民会議会長の伏木 亨先生に、「日本料理の塩加減」についてご紹介いただきます。 -
結節点に在る塩
評論家の雑賀恵子先生に、「結節点に在る塩」についてご紹介いただきます。 -
塩のうまさ
立命館大学食マネジメント学部教授の和田有史先生に、「塩のうまさ」についてご紹介いただきます。 -
食材を変質させる塩の力
作家、生活史研究家の阿古真理先生に、「食材を変質させる塩の力」についてご紹介いただきます。 -
家庭での塩グルメのすすめ
食文化研究家の畑中三応子先生に、「家庭での塩グルメ」についてご紹介いただきます。 -
長野と塩とイカ
湯澤規子先生(法政大学)に、長野県伊那谷の「塩イカ」や、伊那谷への塩の道について、ご紹介いただきます。 -
嗜好品化する塩
髙田公理先生(武庫川女子大学名誉教授)に、塩は、必需品でありつつも、現在では「嗜好品化」しつつあるのでは、という視点についてご紹介いただきます。 -
浜の味噌焼き
落合 功先生(青山学院大学)に、かつて塩の大生産地だった愛媛県の塩浜で行われていた「浜の味噌焼き」、「鯛の浜焼き」についてご紹介いただきます。 -
味覚点描
朝倉富子先生(東京大学大学院)に、私たちが塩味をはじめとする「五基本味」をどのように感じているのかについてご紹介いただきます。 -
これぞ和食!「鯛の塩釜焼」
早武忠利氏(大日本水産会)に、「鯛の塩釜焼」を活用した魚食の普及活動についてご紹介いただきます。